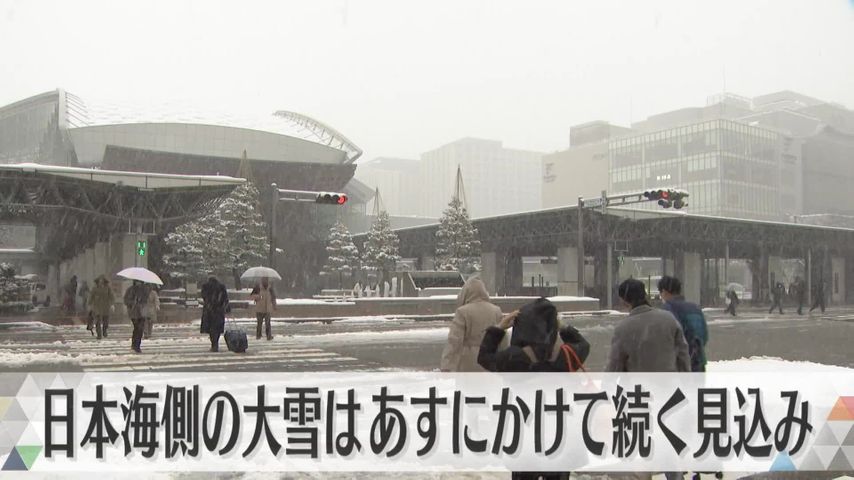中国で日本の酒が人気 魅力もっと伝えたい
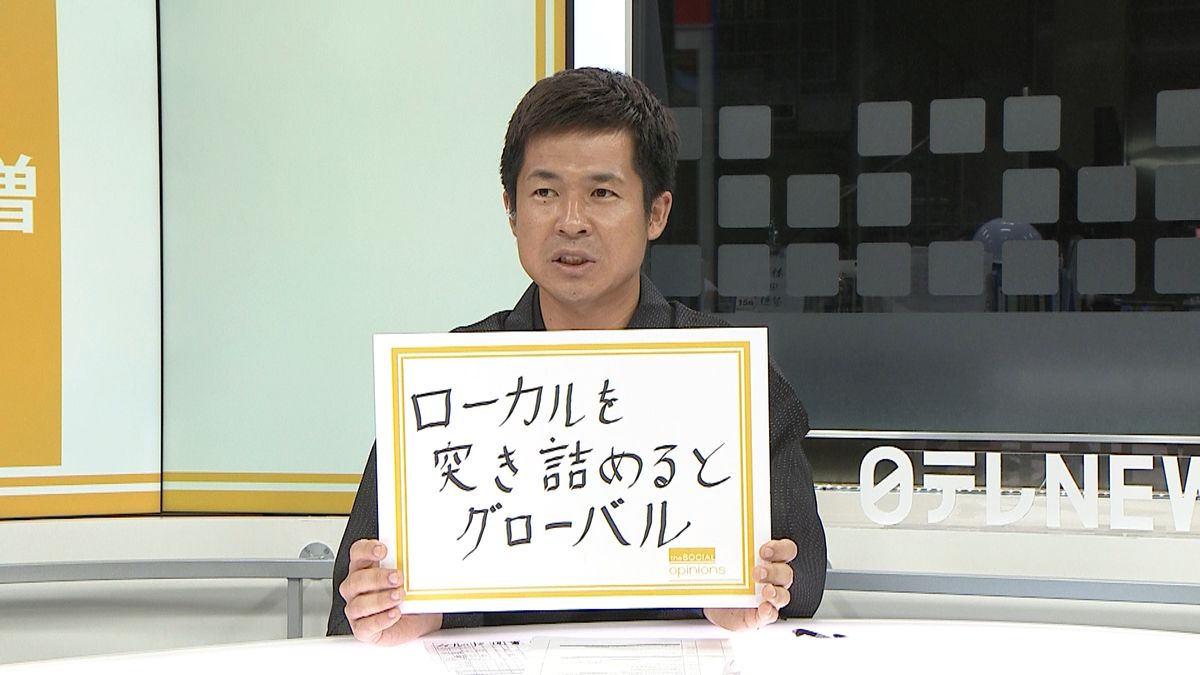
世の中で議論を呼んでいる話題について、ゲストに意見を聞く「opinions」。今回の話題は「日本の酒 中国への輸出急増」。日本の酒を世界に発信すべく“酒によるコミュニティ”づくりに取り組んでいる三宅紘一郎氏に話を聞いた。
今年1月から6月の日本酒などの酒類の中国への輸出が31億7000万円と、前の年と同じ時期に比べて78%増え、大きな伸びになっている。日本食ブームや中国からの観光客増加に伴い、本場の「日本の酒」の味が広まったことが要因とみられている。
ネット上ではこんな意見が見られた。
「中国のマーケットは大きな魅力、まだ伸びる」
「それだけ“日本食”も身近になっているのか!?」
「大陸で日本の酒を買うと、まだまだ高いんだよな」
――三宅さんは、この話題についてどう思われますか。
私自身も中国で日本酒を売ることがあるのですが、いままでは上海や北京などの都市部の方が中心だったのですが、都市部以外の方も日本酒を飲むようになってきたと感じています。
――それがこの急増につながっているということでしょうか。
そうですね。これからまだまだ期待できると思います。
――中国で日本のお酒が人気になってきていることを受けて感じることをフリップに書いていただきました。
「ローカルを突き詰めるとグローバル」です。
中国や世界からお客様がオリンピックに向けてどんどん日本に来ますが、地方で日常的に行われている伝統文化や農業の風景など、そういうローカルの魅力こそが海外の人たちをひきつけると思います。
自分たちが毎日やっていることは大したことないと思うかもしれませんが、実は世界の人たちから見たら、素晴らしいことだということが多くあるというのでこの言葉を選びました。
――そうなると出来上がった日本酒、そのものではなくて、例えば過程はもちろんですが、もっといえば生まれた土地から知ってもらうことが大切ということですか。
なぜこの田んぼを使っているのか、なぜこの仕込み道具を使っているのかなど、そういうところを是非、伝えていきたいと思います。
――三宅さんは、全国の酒蔵などとのつながりもありますが、改めて地域の魅力についてどう感じられますか。
やはり多様性にあると思います。日本の酒蔵は1000以上ありまして、その土地その土地にそれぞれの特徴があるなと改めて感じています。
――まさにそういったところまで、日本のお酒の魅力を知って欲しいですね。
【the SOCIAL opinionsより】